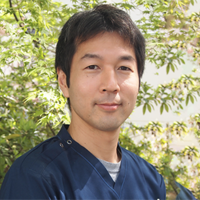座った姿勢を続けると、慢性的な足のむくみを引き起こしやすくなります。特に高齢者の場合、一日中座りっぱなしが続くことによるむくみが生じやすく、高齢化が進む日本では足のむくみを訴える高齢者が増加していると考えられています。高齢者の足のむくみは知らず知らずのうちに悪化していくため、身近にいる方のサポートによってむくみ予防に努めることが大切です。
今回は、横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科 科長の田島 泰先生に、高齢者に起こる慢性下肢浮腫についてお話を伺いました。
増加する高齢者の慢性下肢浮腫
むくみに気付いて慌てる前に、慢性下肢浮腫について知ってほしい
日本は超高齢化社会に突入し、全人口のうち27.3%1)を65歳以上の高齢者が占めています。そして高齢者の増加に伴って増えているものが、高齢者の慢性下肢浮腫です。慢性下肢浮腫とは、病気によるものではなく、高齢者特有の生活習慣(長時間同じ姿勢を取り続けるなど)によって生じる足のむくみです。
足のむくみが生じる病気には、心不全*や腎不全**、深部静脈血栓症***などがあり、いずれも命に関わる病気です。そのため、足のむくみで病院を受診した場合には、これらの病気がないかどうかを調べるために、複数の診療科で全身の検査を行います。
しかし、生活習慣による慢性下肢浮腫の場合、検査を行っても異常はありません。もし、慢性下肢浮腫という病気を知っていて未然に防ぐことができれば、「何か重大な病気ではないか」と不安に感じても慌てる必要はありませんし、不必要な検査を受けることによる負担もかかりません。
残念ながら、日々の暮らしのなかで防ぐことができるはずの足のむくみによって、病院を受診する患者さんが増えているのです。
高齢者の慢性下肢浮腫を予防するためには、普段身近にいるご家族やヘルパー、介護福祉士などが慢性下肢浮腫に関する知識を持ち、原因となっている生活習慣を改善に導いていただくことが大切です。
*心不全:心臓のポンプ機能が低下することで、全身の血液循環がうまくいかなくなる状態。
**腎不全:血液から老廃物や余分な水分をろ過する腎臓の機能が低下する状態。
***深部静脈血栓症:下肢の深部静脈に血栓ができる病気。静脈の血栓が肺動脈に流れて詰まると肺塞栓症を引き起こし、呼吸困難を起こしたり、突然死に至ることがある。
慢性下肢浮腫が起こる原因
慢性下肢浮腫を引き起こす生活習慣
高齢者の慢性下肢浮腫は、長時間同じ姿勢で座りっぱなし・立ちっぱなしでいることや、歩いていたとしても十分な歩行ができていないことが原因で起こります。
長時間座り続けている
高齢になると、どうしても椅子や車椅子に座って1日を過ごすことが多くなります。下肢の血流は、ふくらはぎの筋肉が収縮する力によって足首から心臓へと流れるため、足を動かさずにじっとしている状態が続くと、下肢の血流が滞ります。
すると、余分な血液が下肢にたまり、血液中の余分な水分が血管外へ漏れ出すことで、むくみの症状が現れます。
長時間立ち続けている
長い時間足を動かさずに立ちっぱなしでいることもむくみを引き起こし、特に1人暮らしの高齢女性に多くみられます。
高齢者は一つひとつの作業に時間を要してしまうことが多く、料理や洗濯、掃除などの家事全般を終わらせるのに1日かかってしまうこともあります。すると、無意識のうちに立ちっぱなしでいる時間が増えてしまうため、下肢の血流が滞り、むくみを引き起こします。
歩行が十分にできていない
筋力が低下していたり、膝や足首の関節が悪かったり、パーキンソン病*になっていたりすると、小刻み歩行やすり足歩行になっていたりすることがあります。
このような歩き方では、ふくらはぎの筋肉をしっかりと動かすことができていません。たとえ歩いていたとしても、筋肉によって下肢の血液を押し流すことができておらず、むくみを引き起こす要因となります。
*パーキンソン病:円滑な運動を行うための役割を担う脳の一部に異常が生じる病気。
慢性下肢浮腫はひどくなるまで気付かれないことが多い
慢性下肢浮腫の問題点は、むくみが進行して足がパンパンに腫れ上がったり、強い痛みが生じたりするまで、周囲が気付きにくいことにあります。
足のむくみは日々の生活で少しずつ悪化していきますが、痛みがでるまで症状を訴える方は少なく、周囲の方も高齢者の足を見る機会が少ないために、重症化して初めて病院を受診される方が多くいらっしゃいます。
軽度の段階でむくみの症状に気付き、適切な予防を行うことができれば、むくみの進行を食い止めることが可能です。
次項で具体的な予防法についてご紹介します。
慢性下肢浮腫の予防法
慢性下肢浮腫を予防するためには、主に以下のようなことを実践してください。
- 日中にむくみ予防の着圧ソックスを履く
- 椅子に座るときには、足とお尻を同じ高さにする
予防法1) 日中にむくみ予防の着圧ソックスを履く
足のむくみは、夜寝ているときよりも、日中起きているときに悪化していきます。高齢者の慢性下肢浮腫は、むくみが起きることを未然に防ぐ必要があります。そのため、日中起きているときにむくみ予防の着圧ソックスを履いてください。
着圧ソックスは、ドラッグストアなどで購入できる市販のもので構いません。就寝時にむくみを改善する目的のものであっても、高齢者の場合には日中に使用していただきたいと思います。
また、高齢の方は自力での着用が難しい場合がありますので、その場合には周囲の方々が手伝って履かせてあげるようにしてください。
予防法2) 椅子に座るときには、足とお尻を同じ高さにする


椅子に座っているときには、足を下ろしたままではなく、お尻と同じくらいの高さに上げておくようにしましょう。
このとき、高さ20cmほどの台に足を乗せているだけではむくみを防ぐ効果は期待できません。上図(上)のように、足と同じくらいの高さの椅子などを用意して、日頃から足を上げる工夫をすることが大切です。
しかし、椅子に座るたびにわざわざ足を上げる動作が面倒になったり、腰が痛くなったりして、足を上げることが続かない方も多くいらっしゃいます。
そのため、毎日座る椅子を、上図(下)のようなリクライニングチェアにするなどして、自然と足を上げることができるような生活環境を整えることが理想です。
病気によるむくみの特徴は?
冒頭でもお話ししたように、足のむくみは心不全や腎不全、深部静脈血栓症など重大な病気でも起こることがあり、それぞれ症状の現れ方にはいくつかの特徴があります。
たとえば、心不全や腎不全であれば、足以外にも顔や手など全身にむくみがみられることが多く、息切れや呼吸困難などの症状が現れることもあります。
また、深部静脈血栓症では静脈に血栓が生じるタイミングで足がむくむため、「あのときからいきなりむくんできた」というように、症状発現の時期が明確であることが多いのが特徴です。
ですから、足のむくみと同時にこれらの症状がある場合には、ためらわずに病院を受診するようにしましょう。
むくみが重症化する前に、日々の対策を
高齢者の慢性下肢浮腫を「ただ足がむくんでいるだけで、病気ではないから大丈夫」と軽視してはいけません。むくみが重症化すると、足が重くなったり、痛くなったりして自力で歩くことが困難になり、皮膚潰瘍(皮膚がえぐれて水分が出てくる状態)になったりすることもあります。
最期まで自分の足で歩けるということは、とても大切なことです。そして、それにはご家族や周囲の方々のサポートが欠かせません。
ですから、身近の高齢者が「座りっぱなしになっていないか」「家事を頑張りすぎてはいないか」と日頃から気にかけるようにして、慢性下肢浮腫を未然に防ぐようにしましょう。
【参考文献】
1)内閣府, 平成28年度 高齢化の状況及び高齢化社会対策の実施状況. 2p
横須賀市立うわまち病院 心臓血管外科 科長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。